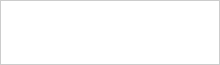ヤマハ No.U3 修理開始

続々と修理予定のピアノが工房に。
運送屋さんが運んで来てくれました
今回はヤマハのアップライトピアノ。「No.U3」
No.U3は、1950〜1970年代に製造された名機で、現在でも根強い人気を誇ります。
「No.」刻印があるモデルは特に初期のものを指し、木材の質や職人の手仕事が光る時代の逸品です。
とはいえ、40年以上経過したピアノは、内部部品の摩耗や経年劣化が進行しています。
長年使っていなかったピアノを弾いてみたら音が狂てったり、鍵盤の戻りが遅い、異音がするなどの不具合が起きてる場合があります。
そのような不具合が起きていたら修理するタイミングでもあり、早めに対処することで修理費用を最小限に抑えられます。

今回のNo,U3もお客様から
「音が出ない所が多々あるし、動きが悪いので買い替えになるでしょうか?」
との相談を受けましたが…
No.U3は中古市場でも高い評価を受けており、適切なメンテンナンス/修理を行えば、今後数十年使い続けることができるので、工房でクリーニング/メンテナンスすることになりました。
No.U3に見られる代表的なトラブルと症状
底板の剥がれ
長年使用していると、湿気や温度差で底板が剥がれたり、裏板がたわむことがあります。これにより音の響きや本体の安定性が損なわれるため、補修が必要です。
鍵盤の引っかかり・戻りの不具合
鍵盤の動きが鈍くなる原因には、木部の歪みやフェルトの劣化、ピンのサビなどがあります。滑らかなタッチ感を取り戻すには、細かな整調が欠かせません。
錆びたピン・クロスの劣化(虫食い含む)
ピンやクロスが錆びたり虫に食われると、動作不良や雑音が発生します。特にフェルト類は湿気に弱く、気づかないうちに劣化が進んでいることもあります。
弦/チューニングピンの緩み・劣化
長年張られている弦やピンは、金属疲労や緩みが発生しやすく、音が安定しません。必要に応じて張弦作業やピン交換が行われます。
金属部分の腐食
ピアノの中にある金属部品が何らかの影響でサビて表面が腐食し、ボロボロになっていることがたまにあります。その際は部品を交換するか腐食部分を除去してもう一度使用できるようにします。
金属の腐食除去
特に今回のNo.U3は金属部品の腐食があったので前編は「金属の腐食除去」/後編は「いつものクリーニング作業」で紹介していきたいと思います。
それではまず、「金属の腐食除去」から作業風景を紹介していきましょー

一目見ると特に問題なさそうな内部機構。
しかし、側面を見ると…

側面がとんでもないことに💦
ピアノの内部に入れている防虫/防錆剤の袋が破けたのが原因。
金属部品にかかったせいで、アルミ部分は化学反応で溶けていて鋳物で出来た金色の部品表面は緑青や錆びでサンゴ礁みたくなっています。

この状態は余りにも良くありませんので、腐食している部分を除去していきます。
表面の塗装も駄目になってるので腐食部分と一緒に塗料も落としていきます。

ある程度まで錆や緑青を落とすことが出来ました。
とはいえ、鋳物の下地がそのまま露出している状態なので表面がクローム色になってますね。
見栄えを整えるためにもう一度、再塗装していきます。

再塗装完了✨
無事、サンゴ礁も取り終え塗装も完了。
最初の状態から大分印象が違くなりました👍
綺麗にした甲斐がありますね。
SNSでも作業風景を投稿しております♪
風が強いですね〜🌪️
— ピアノリペア工房 (@pianorepairkobo) February 13, 2025
今日みたいな日は工房で黙々と作業するのに限る👍
さてさて、引き続きヤマハピアノのクリーニング
腐食した金属の磨きがメインになります🎵
溶けた金属部分はともかく
珊瑚礁みたいなのは除去すればどうとでもなるので…(時間は掛かりますが💦)
取り除いて再塗装します✨ pic.twitter.com/l2cGmkCLjv