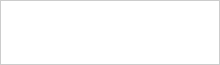ピアノのオーバーホール作業⑦
前回の駒ピン修理作業が完了したので、早速新しい弦を張っていきます。
ピアノ弦は常に強い張力がかかっているため、時間とともに劣化します。
例で言うと古い弦は響きが鈍くなって明瞭さが失ったり、弦が十分に振動できず、雑音(ビビリ音)が発生することがあります。
音程が安定しなくなったら、弦の寿命が近いサインです。
今回のフクヤマピアノも所々、音に違和感があった状態だったので弦を交換することに。

低音部に使われている弦。
ピアノの弦には高音域と低音域で異なる材質が使われています。
これによりそれぞれの音域で最適な音色が生まれます。
巻線弦は音を響かせるため芯線に銅線を巻き付けて重さを増し、響くように設計されています。
しかも既存の巻き線と同等の巻き線を作成するには巻き線屋さんに既存の低音弦をサンプルとして送らなければなりません。

オリジナル巻き線を梱包し、静岡県まで。
届くまで時間が掛かるので先に中音~高音まで使われている芯線を先に本体へ張っていきます。
新しい弦の取り付けは張力の調整と巻き付けの正確さが重要。弦の選び方や取り付け角度に注意して張っていきます。

弦を黙々と張っていきます。
セクションごとに使われている弦の直径が違うため張り間違えのないように注意して張っていきます。
弦は正確な角度で取り付けることが重要。
角度がズレると音質が不安定になります。
それと弦をピンに巻き付ける際は、2〜3回を目安に巻きます。
あまり巻きすぎるとピンが緩みやすくなるため注意が必要です。

さて、中音~高音まで張っている途中に低音に使われる巻き線が静岡県から届きました。
同じ要領で低音も新品の巻き線にしていきます。
弦はただ巻けば良いというわけでなく、弦の巻き付けが不均一だと張力が不安定になり、調律がしにくくなります。
そのため弦が均一に巻かれていると調律の精度が上がりやすいです。

張弦作業の直後は弦が安定せず、音程が狂いやすい。
そのため初回は大まかな音合わせが重要です。
画像は「チッピング」と呼ばれる手作業で、弦をはじいて音を出し、大まかに音階を整えて張力を安定させる作業です。
この作業がとても大事。
そのままにしとくと変な癖がついてしまうので音を上げていきます♪

ある程度、音を上げたら組み上げを開始。
一番のメイン作業が終わったので、あとは修理した部品や内部機構を本体に収めて調整作業に入ります。
Xに作業風景を投稿しております。
本日は工房にて
— ピアノリペア工房 (@pianorepairkobo) October 30, 2024
フクヤマピアノの巻線張り
ようやく形になってきました☺️ pic.twitter.com/kBOfq8ZIn6