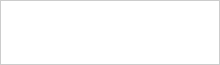内部の調整作業
弦が張り終えたので早速、修理を終えた部品を本体に組み込んでいきます。
今回の投稿と次回の投稿でこの作業ブログは終わるかもですね…
早いものです。

寝かしてあったピアノを起き上がらせて組み込み準備に移ります。
この作業はプラモデルが上がっていく過程を見てるような感じで結構楽しい。

漂白がし終わった鍵盤に修理が完了したアクションを内部に組み込み完了。
弦を張り終えた後に他の修理を始めるとその部分修理に時間が掛かってしまい、変な癖が弦に付いてしまうので、弦以外の修理箇所は弦を張る前に早めに仕上げておくのが良いです。
何よりスムーズに作業に入ることができますからね👍
ともかく、これでようやく調整作業に入ることが出来ます。

半世紀以上経っているピアノの場合、現在の調整方法とはまったく別物です。
現代のように既定の鍵盤の高さや深さ、弦とハンマーの距離は決まっておらず、臨機応変に調整するのが主流のため一度目はザっと全体的に揃えていきます。

1回目、2回目、3回目と水をろ過していくように何度も繰り返し調整を行っていきます。
繰り返し調整することで内部の精度を上げていくことができるからです。

特に鍵盤のタッチはmm単位の世界になるため全ての鍵盤の高さ/深さを均一に調整していかなくてはいけません。
左の青い丸紙(厚さ0.08mm)一つで鍵盤のタッチは変わります。
黄色の丸紙が0.15mm、赤色の丸紙が0.30mmと厚さが違うので適切な紙を選んでいきます。

適切な紙を選ばないと鍵盤を押した時の深さが深すぎたり浅すぎたりして連打がしにくい、二度打ちしたりといった症状が出る場合があります。
特に象牙は一本ずつ厚みが違うので慎重に紙を選んで調整を施していきます。

ビンテージモデルのピアノの場合は2~3回繰り返し調整することで安定していきます。
最初と比べて徐々に精度が上がっていくのを確かめながら作業できるので、結構楽しい。
今回は全ての部品を分解した影響なのか4~5回ほど繰り返し調整をしてようやく落ち着きました。

ということで、調整作業は完了。
ゴールまであと少し✨
次回の投稿はちょっとした作業を紹介して終わるかな?
それでは、また👋
Xでも作業風景を投稿しております♪
フクヤマピアノの調整作業🛠️
— ピアノリペア工房 (@pianorepairkobo) November 7, 2024
厚みが違うペーパーを使って鍵盤の高さを揃え中🎹
鍵盤と定規との間に隙間がないようにしていきます。
とりあえず、安定するまで2〜3回ほど調整作業を繰り返す。
1回目は大まかに、2回目からは徐々に精度を高めていきます🎵 pic.twitter.com/qA89hZ3wIJ